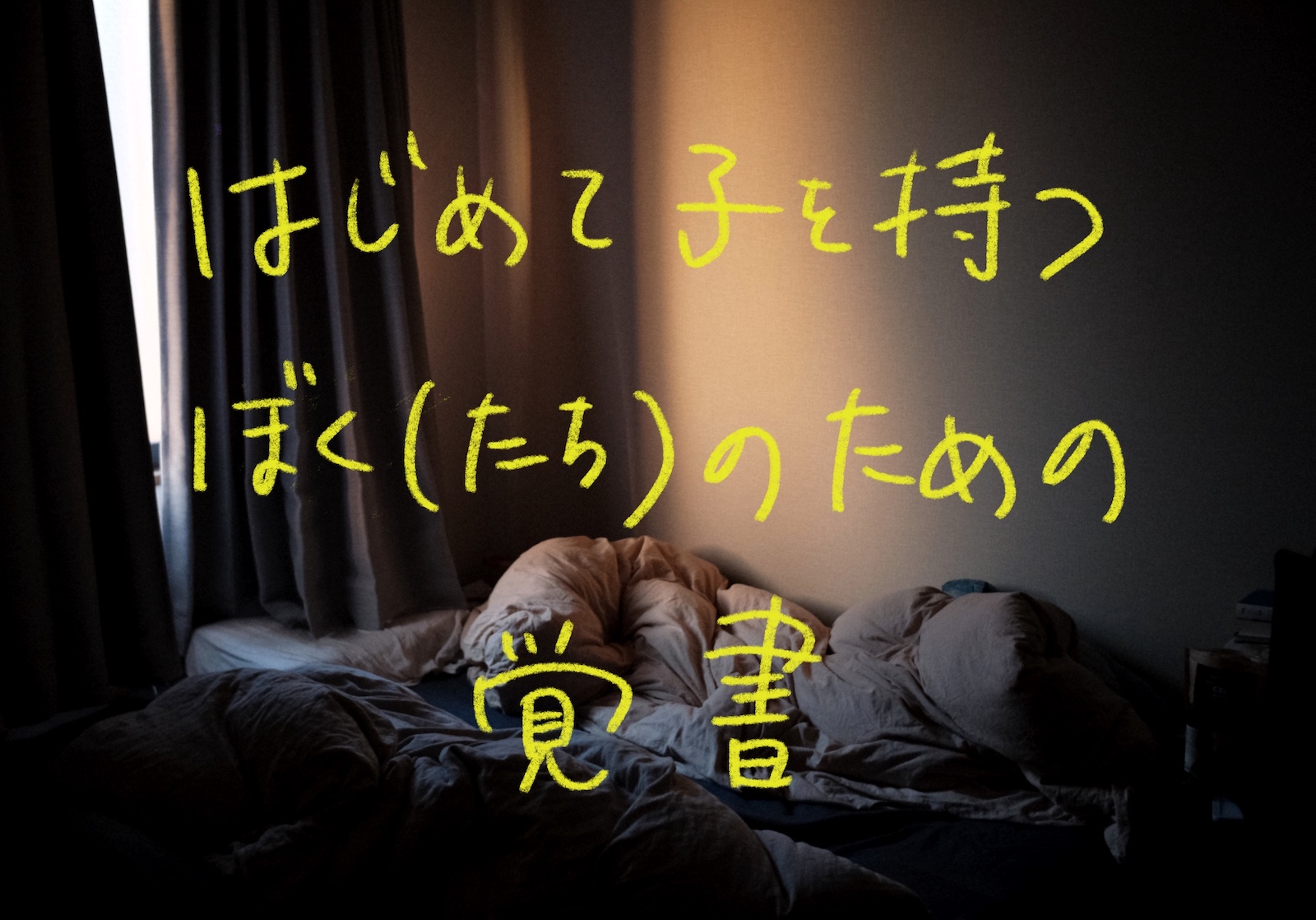これまでの連載はこちらから
20週をすぎてつわりがおさまってきて、少しずつ胎動がはじまった。
「ビー玉がころん、って転がるみたいなんだよ」
そう妻がいうのを、ぼくもなんとか感じてみたくって、夜ごと寝る前におなかを出してもらい、そこに目を閉じながら手を当てる。魚を釣るときにアタリを感じるようにして、やっと手に感じたその手応えで、この「はじめて子を持つぼく(たち)のための覚書」ってタイトルをつけたエッセイの1回目が書かれることになった。
ここに来て、どうしても妊娠に関して当事者たり得ないことに、だんだんぼくは不満のようなものを感じ始めていた。彼女のからだは毎日のように変化するのに、なんにも変わらない自分の身体感覚に焦りみたいなものを感じはじめたある日、自分にしかできないこと、自分の方がその変化を先に感じられることはないか、考えていた。でもぜんぜん見当もつかない。
たまひよのアプリをひらいてみる。
たまひよっていうのは、ベネッセがやっているアプリで、予定日などを入力すると、そのときどきの赤ちゃんの姿がイラストで表示され、いまどんな状態なのか、何に気をつければよいのかを教えてくれる。ユーザーは自身の性別を入力するので、ぼくの場合は「今日のパパへ」というコーナーがある。

ぼくたちの「胎児ネーム」はおまめちゃんなのだけど、もうぜんぜん豆っぽくなんかないから、呼んでいない。あと「胎児ネーム」って概念は、ちょっぴり不気味な感じがする。
これを書いている今は33週で(なんてあっという間なんだ!)、「今日のパパへ」では、チャイルドシート義務づけの話から、はやいうちに用意しときな、ってアドバイスが書かれてる。
最初はまめみたいだったイラストの赤ちゃんが、今では、ちゃんと人の形になっていて「トクトク」って謎のことばを発しているのを見て、ひらめいた。胎動で動くおなかを見るのは、ぼくが先にできることなのかもしれない。ってゆーか、この「トクトク」ってことばじゃなくて、胎動そのもののことなんじゃない?
その日から、寝る前に目を閉じて手を当てるのではなく、目をじっと見ひらいて、おなかが動かないか注意することにした。でも、そうやってガン見している時には、不思議なことにうんともすんとも言わない。
「おおい、おおい」
呼びかけてみて、まだ名前のないこの子になんて呼びかけるのがいいんだろう、と思う。
「……あかちゃん~。おきてる? こちらはパパですよ」
そうやって、おへそをとんとんとしてみる。ここの内側からへその緒を通してあかちゃんにつながっているわけで、ここを押せば、なにか気持ちが通じるような気がして、とんとんと押す。
そうやって過ごすこと1週間。
その日の夜も、いつも通りにおなかを出してもらい、じっと見ていた。10分ほどそうしていただろうか。カッと見ひらいていた視野のはしっこ、脇腹のあたりが、ちょこん、という感じで膨らんだのをぼくは見逃さなかった。
思わず「よっしゃー!」と叫ぶ。
妻は「よかったねー」とフラットなトーンでいったから、自分の感動をばかばかしく感じて、照れ隠しで彼女に抱きついた。もちろん、おなかを圧迫しないように。そうしてくっついたまま「動いたの見えた!」とジタバタしているそのとき、ああそうか、この「ふたり」を同時にハグできるのは、自分だけなんだなあ、とじんわりとした感動の中で思ったのだった。
■
今年はご縁が回収されていく1年になる。
と漠然と思っていた。
そしてぼくの場合、だいたいそういう思いは現実になるもので、昔仕事を一緒にしていた仲間だったり、そのときお世話になっていた先輩だったり、そういう人と再会する機会が増えていった。
奥村と久々に会ったのは下北沢で、一緒にメディアを立ち上げて運営していた仲間4人で、5年ぶりくらいに集まった。そのメディアはなんというか、けっこう劇的な終わり方をしていて、それぞれに重たいものを抱えながらチームはちりぢりになっていたから「あのあと、みんなどうしてた?」って、お刺身をつつき合いながら話し合う。この感じどこかで経験したことあるな、と思ったら、それは東日本大震災のあと、仲間内で集まって、ため込んだ思いを語り合っていた時間に似ていた。
ひとしきり仕事まわりの近況を報告しあうと、「じゅんちゃんの調子はどうよ」ってわが家の話になった。この中で子どもがいるのは奥村だけだ。夫婦ともにフリーランスで、ふたりとも会社組織に所属することなく仕事をし、分担しながら子育てをしている。子どもは1歳を過ぎたあたりらしい。この日も彼は「寝かしつけがあるから、ちょっと遅れて参加さしてもらうわあ」といって、あとからいそいそとやってきた。
「あの、武田の妊娠のエッセイ読んだよ」
「お、ありがと。どうだった?」
「いや~、めっちゃよかったわ。武田のテキスト、今まで色々読んだけど、その中でもいちばんよかった」
「まじか。でもなんかそれけっこういわれるんだよ。1回目出したあとも、想像してないくらいの反響があって」
「いやあ、そうだろうなあ」
「なんだなんだろ?」
「なんでやろ。まず技巧が挟まる余地がないくらい、切実な感じがするからじゃない? あとは──男女とも、それぞれの視点で読めるからじゃないかな」
「なるほどね」
「おれは、懐かしい気持ちで読んだ。ああ、そういう時期あったなあって。でも、その時の感覚すらもう忘れちゃってんの。こっちはこっちのタイムラインで、子どもが日々変わっていくからね」
「やっぱそうか!きっとそうなるって思って、だからぼくその時々の感じを書いておきたいって思ったんだよ」
ぼくが書き始めたのは、自分自身がどうしても当事者として経験できなくて、どうしてもわからない感覚に、なんとか近づきたかったからだった。そして、子どもや子育てに関して、男性側からの視点で記された言葉の中に、自分が必要としているものがあまりにも少なく感じたからだった。
もちろん男性視点の育児エッセイや、そのノウハウを記した本はごまんとある。でも、どこかしっくりこないものばかりだった。勉強にはなるし、なるほどと思わされるものもある。けれどそこに記されている言葉たちは、どこかよそ行きなものに感じる。夫がメインで労働を担当する中で、どう妻をケアできるのか。あるいは、専業主夫になってみました。男性視点での育児ものって、そのどちらかが多かった。
ぼくが知りたかったのはそうではなく、どうしたら労働も育児も、どちらかに寄りかからず、できる限りフラットに、それぞれの得手不得手を補いながら、生活設計ができるのかってことだ。どちらかのわかりやすい極に寄るのではなく、その間の広大な荒野みたいな空間で「うちらは今この辺でこうやってるよ〜」っていう、素朴なキャラバンからの声を聞きたい。
目の前には、おそらく子どもが産まれたあとぼく(たち)が行う生活様式に、かなり近い形でやっている、そう思われる友人がいる。ぼくは夢中で言葉をぶつけた。
仕事はどうしてる?
仕事場は今あるの?
保育園の送り迎えは?
ミルクは?
そっか、それで寝かしつけは担当してるのね。
子どもはちゃんと寝てくれる?
寝てくれたあとの夜の時間は、どう過ごしてる?
休日ってある?
奥村はひとつずつていねいに答えてくれたあと
「でもな、結局ブラックボックスやねん」
といった。
「どういうこと?」
「今話したことは、うちの場合やん? 何かが起こる。たとえば何の理由かわからないままずっと泣いてて、いろいろ試したらこうだった、みたいな」
「うんうん」
「そこで学んだ『こういう時にはこうするといい』って知識も、あくまでうちの場合だし、なんなら、『うちのその時の場合』でしかない時もある」
「わかる気がする」
「もちろん最大公約数的な知恵ってあると思う。でも『こういう時にはこうしたらいい』も『これがこういう時に便利』も、あくまでそれぞれのケースによって違うんよ。しかもそれは、時々によっても変わる」
「そうだね。子どもには個性があるし、親のぼくたちにもそれぞれ特性がある」
「せやねん。だから、いろいろいうたけど、最終的におれからいえるのは、武田の前にもブラックボックスが来るよってこと」
「それで、ブラックボックス、ね」
「そう。入れたらどう出るかなんもわからんまんま、都度それに対処する。そういう時間がくるよってことくらいだわ、いえるの」
子どものいない残りふたりの前で、これ以上話を続けるのはなんか悪くて、ぼくたちは再び懐かしい話に戻っていった。思い出のつながりは心地がよくって、なじみのおばあちゃんのスナックに場所を移して、それをしばらく続けた。
終電が近づいて、みんなで駅に向かう。
下北沢の町は再開発で大きく変わった。けれど変わらないものが地下水脈として流れていて、それはかつてぼくたちがこの町で身を浸していた懐かしい流れだ。そのにおいを覚えているぼくたちは、今が時期だと感じて遡行した。その先に、たとえば今日があった。昔なら電車なんか気にせず、いつまででも話し合っていた。話すことに満足したら、会話は歌に変わって、それで気がつけば朝になっていた。
やってみないとなんもわからない、ということがわかっていく。そのことは、具体的で処方箋的な知識を得るより、なぜだかずっと頼りがいがあって、わくわくさせられるものだった。ぜんぶ初めてで、なにもわからなくて、だから色々試してみる。それってきっと、自分が生まれ直すことと、ほとんど一緒だ。
23時半。またねといって、井の頭線の改札に向かう。
ひとりになって、奥村が過ごしている夜の時間のことを思う。子どもが生まれてから、ほぼ飲みに出かけなくなった。1年が経って、だんだん自分たちの暮らしの輪郭が出来上がってきて、でもそれがまたすぐに形を変えうることに気づいてる。
変わっていくことと、それでも変わらないことがあって、飲みに出かけなくなっても、2人で協力ができたなら、こうやって子どもを寝かしつけてから、21時くらいに合流することだってできる。終電まで3時間。そうして生み出された夜の時間は、彼にとってどんなものなんだろう。
場所の変わった井の頭線の改札に体を滑り込ませながら、あああ、と声が漏れる。変わっていくなあ、変わっていくんだなあ。
2015年、ぼくは井の頭線の西口を出て15秒の場所に住んでいた。毎日フリーランスで働く誰かがやってくる家で、ニートピアなんて呼んでいた。そのあと引っ越しを数回重ね、2021年まで、ここから徒歩15分くらいのところに住んでいた。だから下北沢には、電車に乗って帰る思い出がない。
変わっていくことと、変わらざるを得ないことの中を進むから、きっと変わらないでいるものの存在に気がつける。来年、ぼくは子どもを寝かしつけてから、こうやって懐かしい仲間に会ったりするのだろうか。1年先を示す想像の矢印の先端に奥村を置いてみると
「だから、武田、ちがうって? ブラックボックスいうたやろ?」
とかれはいった。
電車が動き出す。5センチぶん開け続けられている窓から、少しだけ秋めいてきた風が入る。気持ちが変にたかぶることも、さびしさに突き落とされることもなく、ただじんわりと心地がいい。そういう今の自分たちらしい夜の時間が、終わろうとしている。
つづきはこちら
4|弱いまんま生きてゆけ