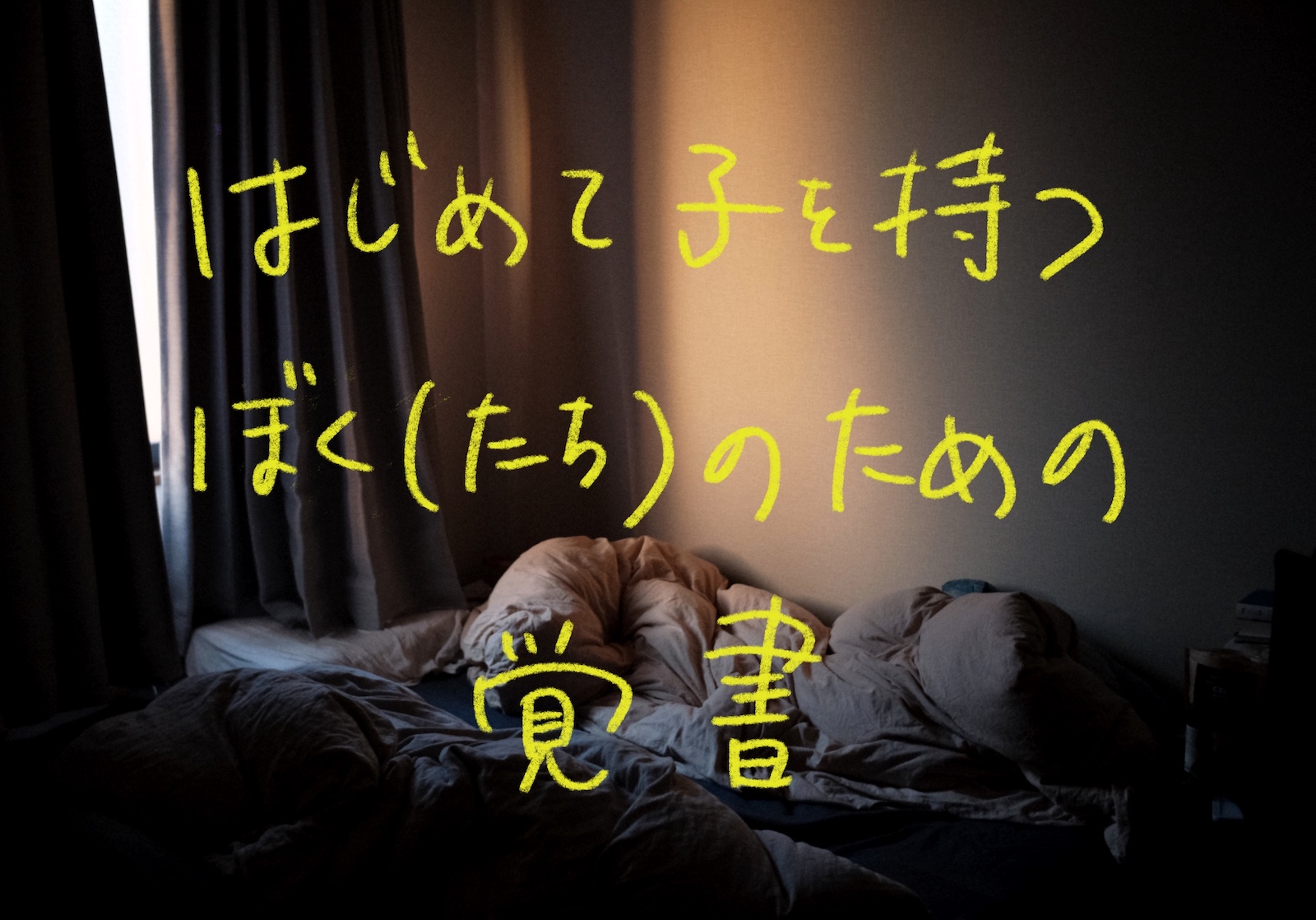これまでの連載はこちらから
#1|そもそもアンバランスな人生
#2|つわりのおわり
#3|ぼくだけにできること?
30週を迎えて、いよいよ妻のおなかがぼーんと日に日に前にせり出してくるように大きくなった。もともと長身痩せ型の人だから、ぽこんとしたおなかは目立っていて、おもしろいなあと眺めている。ハンプティダンプティみたい、というと、不服そう。
特におもしろいのはおへそで、もともとはへっこんでいたそこは、前にせり出すおなかによって皮膚自体が張り出していくから、裏返っていくのだ。裏と表が入れ替わる。ソフトコンタクトレンズが、持ち方を誤ったときにくるんと形を変えるときのように、おへそが入れ替わる。そういうことはあまり本には書いてなかった。妻はよくその出てきたおへそをそうっと指でつつきながら本を読んだり、スマホを見たりしている。それがぼくには、おへそを通じておなかの子と交信をはかりながら、日常の作業をしているようにみえてうらやましい。
そんな時に、ひさしぶりの人からLINEが届いた。
高校時代につきあっていた、女の子からである。
人にはいろんな恋愛のしかたがあると思うのだけど、ぼくはその時々のパートナーからものすごく影響を受けるタイプで、きっと恋愛体質なのだけど、この人は当時京都の大学への進学を考えていたぼくに渇を入れ、東京に連れ出してくれた人で、つまり現在のぼくの有り様の基礎をつくってくれた人ともいえる。
不思議なことにお別れをしたあと(大学1年の夏にふられている)も、人生の重要な局面にふわっと連絡をしてくれて、それが何か新しい風を呼ぶ、みたいなことがこれまでもあって、今回はまさに育児のあれこれについてだった。特に、ぼくの体調について、自治体や保育園のやりとりを進めていく際に参考になることを教えてくれていた。
この連載の中でもぼんやりと自分の不調について触れたけれど、ここで今一度書いておこう。ぼくにはとある精神疾患がある。最初は双極性障害と診断され、そのあと特殊な診断名に変わった。最初に診断をもらったのが2013年、今の診断名に変わったのが2014年のことだから、トータルでこの病気とつきあってきて10年目になる。今でも投薬治療は続けていて、3ヶ月に1度、地元愛知県の主治医のもとに通っている。
この病がもたらす世界の風景について、ちゃんと記そうと思ったらそれこそ1冊の本では足りないくらいなので、ざっくりにとどめておくと、ぼくの場合、躁と鬱のエピソードがかなりラピッドなサイクルで切り替わっていく。多いときには、ひと月の間にそれらが数回やってくるし、なんなら1日の間にすら、上げ下げをくり返したりもする
鬱という字がきらいなので、落ちる、といういいかたをしたいと思うけど、落ちるとほんとうに世界から色が失われて灰色に見える。体重は数倍の重さになって、立ち上がることすら一苦労。そして、ひどいときには顔の見えない集団がぼくのことを責め立てるための会議をはじめる。さらにひどい場合、かれらはぼくに自ら命を絶つよう命じたりもする。
そんな希死念慮を乗り越えた翌日、世界中が新緑のあかるい光に満ちあふれたように輝き、何を食べてもおいしく、外に出て歩くと1歩足を踏み出すあいだに新しいアイディアが新芽のようにぽこぽこと顔をのぞかせたりする。人と会えば絶妙なバランスでジョークが繰り出され、怒濤のようにしゃべり、にもかかわらずあらゆる局面で気遣いもかかさない、そんな余裕すらある。さらに上がると、飛び出してくるアイディア自体がその場からどんどん仕事になっていき、会社をつくったりしはじめる。昔は何かの会話をトリガーに、手をつけられないほど怒り出したりすることもあった。今ではそれはほとんどなくなったけれど。
この極端な波の中で10年生きてきたのだけど、いちばん困るのは、それぞれの極にいる時の記憶のセーブデータが共有されないことだ。落ちている時に、どんなことがあり、何を考えたかは覚えてる。けれど、一度その落ち込みからなんとか脱出できた途端、昨日までどんな風につらくて、何に困っていたのかはまったく思い出せない。これは、逆もしかり。
こんな揺らぎの中で生きているから、ぼくはぼく自身の感覚や実感を信じ続けることが難しい。だからこうやって書いたりするのだと思う。そして、それを人に見ていてもらいたいと思う。ぼくに内臓されている記憶媒体は極端な情緒によって、遮断される。そういうピーキーなものだから、外部のメモリを必要としているのだろう。だからぼくの書いたものはすべて、宛名のないまま記されて瓶に詰めて海に投げられる手紙のようなものだ。
宛名がないということは翻って、すべてこれを今読んでくれている「あなた」に向けられている、ということでもある。
■
3回ぶん書いてみて、なんだかお互いを慈しみあって、男性である書き手が相手のことを慮っている、今ふうな、すてきなエッセイみたいになってる気がして、ああかっこつけて書いてるところ多いなあって思う。スマートにやってる感じだけど、ぜんぜんそうじゃなくって、ええい、今日はださいところをちゃんと書いておきたい。
ぼくがこんなピーキーなものだから(そして実は妻も妻でなかなかユニークな特性を持つひとなので)ぼくたちは付き合いはじめた時から、なんども大きなけんかを重ねてきた。それでも結婚6年目、ほぼほぼ平和に過ごしているのだけど、久々にお互い自分が何に怒っているのかわかんないくらいのけんかになったのが、妊娠10週すぎのとき。
そのたねは出生前診断だった。
出生前診断は文字通り、生まれてくる子の状態について、調べるものだ。おもに染色体の異常からなるダウン症や18トリソミー、13トリソミー、開放性神経管奇形についての可能性を調べることができる。
ぼくはそもそも受ける必要をまったく感じていなかった。
というのは、個人的な体験による。
小学校の6年のあいだ、ダウン症や自閉症の子たちと健常者の子どもが、一緒にキャンプやクリスマス会などの年中行事を行う子どもクラブみたいなのに入っていた。1年生だと、6~7歳か。それまでダウン症の子と関わったことなんてないから、最初は自分と見た目の違う子たちの存在に対して、こわさ半分興味半分といったところだったのだけど、一緒に岐阜の山奥でキャンプをしてカレーをつくり、ペンライトひとつで肝試しをしてゆくうちに、見た目やことばの使い方の違いなんて、あまり気にならなくなってきた。
年上でもことばの習熟が自分よりも幼く感じられたかれらに対して、どこかお兄さんのような気持ちで接する時に、自分自身にはじめて頼もしさを感じて、だからどんどん助けてあげればいいって思った。
キャンプの最終日には、そのクラブの大きな広間で長机に向かって、この3泊4日の時間を振り返る絵日記をつけることになっていた。早々にそれを片付けたぼくは、前からふしぎに思っていたことを、スタッフのひとに聞いた。
「ねえ、なんでダウン症って子どもばっかなの? おじいさんとかおばあさんは、なんでいないの?」
スタッフの男性はなんともいえない表情を浮かべてしばらく黙ったあと、ゆっくりとこういった。
「あのね、ダウン症っていうのは、ふつうの人みたいに長く生きられないの」
全身を熱いものが駆けめぐって、言いようのない気持ちがあふれだした。それは怒りにとても似ていた。なんで。どうして。キャンプで一緒に遊べて、なのに、なんで。気がつくとスタッフにぼくは背中をとんとんとさすってもらっていて、それで自分が泣いていることに気がついた。
調べてみると現在では医療の発達もあり、ダウン症の方の平均寿命は60歳前後まで延びているらしい。1970年代には10歳ともいわれていたようで、ぼくがかれらと過ごした90年代には、たしかにダウン症の老人というのはあまりいなかったようだ。
当時のぼくの怒りをいまことばにするなら、がっかりと不公平が入り交じった感覚だったと思う。自分たちと何ら変わらない、とまではけっして思わない。見た目もことばも違う。ぼくがそのキャンプでつかんだ実感は、そんなふうに違うように見えるひとたちと、何ら変わらない時間を一緒に過ごせたというもので、そんなかれらを自分はケアできるのだという頼もしさで、それは絵日記を書いたあの大広間に山からの風がすーっと抜けていくような気持ちよさがあった。なのに、なんで生まれつきでこんなに不公平なのか。
だから、妻が出生前診断に興味を示した夜、会話を重ねてゆくにつれて、ぼくはダイニングテーブル越しに烈火のごとく怒りをぶちまけた。
「じゃあ聞くけどさ、なんで受けたいわけ?」
「……わからないけど、でもなんか不安だし、受けてみたい気がするの」
「気がする、とかで決めていい問題じゃないよ。受けてみたいのはわかるけど、でもそれでダウン症の可能性があるといわれたら、君はどうするわけ?」
「それは、受けてみないとわかんない」
「何ぬるいこといってんだよ! 診断を受けるってことは、命の選別の場に立ちうるってことだよ」
「うん、わかってる……」
「わかってるなら、あなたは命の選別をする覚悟があるってことなのね」
「え、そういうことじゃないよ」
「じゃあなんなんだよ!」
「わかんないよ。生まれる前に障害があるってわかっている子を、育てていく自信があるのかもわかんない」
妻の煮え切らない態度に、どんどん怒りが増していく。
「だったら受ける必要ないでしょ。仮にダウン症の可能性がある、と結果が出たとするよ。そこで堕ろすなんてことは、ぼくはぜったいにおかしいと思う」
「別にそうしたい、とはいってないでしょ」
そういった彼女のおなかを見ながら、ぼくはいった。
「だったら受ける必要がないんだって。堕ろすかどうかっていう選択肢を手にする必要がないっていってるの。命の選別なんてことばは生ぬるいよ。生きようとしてるんだよ。生の冒涜だよ、虐殺だよ」
最悪だ。いったそばからまずいと思った。ことばがきつすぎる。妻は下を向いたまま、もう何も話そうとしなくなった。身体ぜんたいを支配している熱をなんとか冷まさないといけないと思って、自室に向かう。その日はそれっきり話もせず、眠った。
翌日、冷静さを少し取り戻した頭で、そういえば出生前診断ってどれくらいの確率でわかるんだっけ、と思って調べてみた。出生前診断には、非確定検査と確定検査のふたつがある。非確定検査にも何種類かあるようで、新型出生前診断であるNIPTというのは精度が高くて、最近主流らしい。これは採血するだけ、というのもメリットが高い。
ただ文字通り、これは非確定検査で、その精度は99%とのこと。仮に陽性と出た場合には、それがほんとうに正しいのか確定検査に進む必要がある。99%というと、ほぼ100という感じがするが、100人にひとりは外れ値になると思えば、なんだか低いという感じもしなくなってくる。
で、この確定検査というのがやっかいだった。
確定なので100%の結果が出るのだけど、妊婦のおなかに針を刺して(それだけで、とても気が進まない)、羊水あるいは絨毛(このあと胎盤になる組織)から抽出したもので検査をする。やっかいというのは、羊水の場合300人にひとり、絨毛の場合100人にひとり、流死産のリスクがあるということ。
想像してみた。非確定検査を受けて陰性だったなら、まあ問題はない。「ひどいけんかしちゃったけど、陰性でよかったね」でおそらくすむ話だ。陽性だった場合、どうなるだろう。まだこの段階では、非確定なわけだ。一縷の望みをかけて、リスク承知で確定検査に進むのだろうか。それで流産にもでなったら、どんな気分でそのあとの人生を生きていけるのか──。
ちょっと待てよ、今「一縷の望みをかけて」っていったよな。なんだよ、それ。なら陽性だった場合、つまりダウン症もしくは染色体異常のある子は、絶望だっていうのか? かれらの生には、意味がないとでも?
いや、っていうか、そもそも生に意味なんて、必要なんだっけ?
ふと、妻とつきあい始めて最初のころにしたけんかを思い出した。
けんかというか、それは議論のような話し合いだった。
さっきまで楽しく過ごしていた彼女が、不安な表情を浮かべていて、瞳が揺れている。なんか変だな、と思ったら、彼女のラップトップに表示されていた検索窓に「双極性障害 結婚」という文字が浮かんでいた。双極性障害当事者との結婚はおすすめできない、わかれなさい、病気が子に遺伝する可能性もある……。ろくでもない結果が表示されていることを、知っていた。なぜなら、最初に診断名をもらったころ、同じワードで検索をしたことがあるからだ。
ひとしきり話し合ったあの日、ぼくは彼女にこういったはずだ。
「病気については、もっとぼくも学んでいく。知識は共有する。だから病気じゃなくて、そういうぼく自身を見て」
と。
すぐ妻の部屋にいって、昨日のことをあやまった。彼女もごめんね、といってくれた。それで、さっき調べた出生前診断の情報をシェアした。ぼくらはお互いに、検査のくわしい仕組みや、そのリスクについてしっかりと知る前に、立ち上がる不安にからめとられて、情緒的な側面ばかりでけんかをしてしまっていたようだった。
やっぱ正しい情報や知識って大事だねえ、と話しながら、で、どうしよっか、とふたりで考える。そういえば、費用ってどれくらいかかるんだろう、とそこでまた調べると、確定検査までやるとなると、20万円ほどになるという。
「払えない金額じゃないけど、なんか思ったより高いねえ」
「じゃあ、ま、やんなくていっか」
昨日数時間、感情を互いに爆発させて話し合ったわりに、なんとあっけない幕切れだろう。そう思ったら、途端に気分がぐんぐん上昇し、世界がまたうまれたてのような、きらきらとした光に包まれていった。ぼくはその勢いのまま、ほがらかな気持ちで尋ねてみた。
「それにしても、なんで昨日あんなに、かたくなだったのよ~」
「ん、どういうこと?」
「検査のくわしいこと知らないのに、ずっと『なんか不安だから受けてみたい、かも』ってくり返してたじゃない」
彼女は、なんで当たり前のことを聞くの、とでもいう風に、からっと笑いながら
「だってね、このおなかの中で、今、毎日いろんなことが起こってるのよ。だから毎日『なんか不安』だし、いつも『わからない』んだよ」
といい、席を立って振り返りながら
「だから、かわりに調べてくれて、ありがと」
といった。
ショックだった。ぼくは自分の側のほうしか見ていなかった。幼少期の自分の体験と、そこから育まれた倫理観のほうしか見ていなかった。それをただいきなりテーブルの上に叩きつけるだけで、そんなの対話でもなんでもない。
変化はいまのところ、常に彼女の、そのからだの内側で起こっている。なら、知り得ないその感覚や情緒を最優先するのがいい。それが当然だと、やっぱり思う。それでやっとちょうど、なんていうか、半分ずつになる気がする。知識は共有した上で、まずお互いにあなた自身を見る、ということ。
■
そのときから20週だから、5ヶ月くらいが経ったことになる。
その間にぼくは、6回落ち、6回浮上した。
これから子どもを持つというのに、つらくて今すぐここから消えてなくなってしまいたい、そう感じてしまう自分のことがわからなくて、信じられなくて、情けなくて、なんども泣きついた。生きていくということにつきまとう苦しさがこれほどにあるのなら、なんで生まれてくる必要があったのだろう。そこで足掻き続けることに、いったいどんな意味があるのかとずっと考えてしまう。そんな人が、子どもを持っていいわけがない。そんな考えの隘路にはまって出られなくなっていた。
でも、ずっと前から知ってもいるのだった。
生に意味とか必要とか、ない。生まれてきたくて生まれた人は、誰もいない。ただ、生きているだけだ。ただ、今、ここにあるだけだ。そこにどんな意味や価値を見いだすかが人生で、だから人間は美しい、なんてステレオタイプで口当たりのいいことも信じられない。
いいたいのはそんなことじゃなくて、ただぼくらはここにあるだけだ、ってことだ。そこに意味とかはない。だからただ、その瞬間瞬間の連なりを、どう言祝ぐことができるのか。そのやり方を探すだけの時間があって、それをどう味わっていくかってだけのことなんだろう。
きっとぼくはこのままの状態で、父になっていく。
この弱さを、脆弱性を抱えたまま父になっていく。
それでいいのだ。
運命には変わらず、抗ってやる。でも、症状は受け入れる。絶え間なく観察する。どうやって、マシにできるかを考えながら。
そうした時間の中で、自分はいったいどんな風に変化していくのかが楽しみだなあと、今、思っている。めったにやってこない、この上がりも下がりもしない、はじめてなのに懐かしい、緩やかな凪の時間の中で思っている。
つづきはこちら
#5|イオちゃん、おはよう